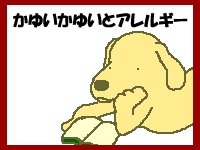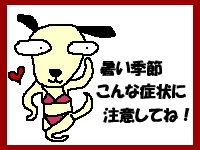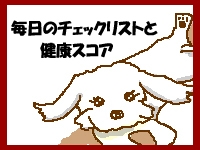毎日のチェックで元気に過ごそう
毎日のチェックで元気に過ごそう
みんなブラッシングは毎日やってもらっていますか? ロン毛の子もショートカットの子も毎日のブラッシングタイムは スキンシップだけではなく大切な全身チェックの時間。 皮膚炎も外耳炎も歯周病もある日突然発症して その日のうちに一気に悪くなるものではありません。 毎日チェックしていることによって、「早期発見!早期処置!」が可能です。 悪くなってしまう前にちゃんと毎日チェックしてもらいましょうね。
ブラッシングではお腹以外は皮膚の状態までは見えません。 うちではブラッシングした後で、コーミングで毛をかき分け皮膚の状態をチェックします。 あと、お風呂タイムは皮膚の状態チェックに良いですね。 ぬるめの温度でドライアーをかけながら皮膚を観察してゆくのもわかりやすいです。 ダブルコートの子はちょうど今は換毛期で大変な季節かな? 下毛をしっかりすくい取ってもらいながら、皮膚もチェック。 これからは気温が上がってくる季節ですので、皮膚のpHがアルカリ性に傾きやすく 皮膚コンディションが崩れやすい時期、しっかり毎日チェックしてあげてくださいね。
わんこの皮膚にはいろいろな変化が起きます。 原因がはっきりしているものは原因を除去するだけで 早いうちに自然治癒するものもあります。 そのためにも日ごろから自然治癒力を養っておきましょうね。 ダニやノミが引き起こす「痒い痒い」に対してはずっと以前のお勉強室の 「痒い痒いとアレルギー」 で詳しく触れています。 ここでは「防ぎ方」も記載しています。 10年前なのでまだ新インセクトシールドもなかった頃で、ある意味懐かしく新鮮です。 また 「暑い季節!こんな症状に注意」 のページでも別の視点から触れています。 あわせてご参考になさってくださいね。
ここではかる~く復習の意味で「痒い痒いとアレルギー」の一部を転載しておきます。 原因
特徴と処置・注意点など
Demodectic Mange 毛包虫症
- 皮膚の皮脂腺に寄生し、毛包虫症という脱毛や皮膚炎をひき起こす病気になります。アカラスとも言われます。
- ニキビダニは多くのわんこに多少は寄生していると言われますが、健康なわんこの場合は抵抗力があるため大量に増殖せず、症状は現れません。免疫力や抵抗力が低下すると、症状が現れやすくなります。抵抗力の弱いパピーやシニアに多いので、初期症状の脱毛にいち早く気づいてダニ駆除とあわせて治療してください。眼の周りや口の周りに脱毛が起きる症例が多いです。
Scabies 疥癬
- イヌセンコウヒゼンダニによって引き起こされる皮膚病です。このダニは感染している犬の首輪やブラシなどから感染します。お散歩の草むらに感染したわんこが落としていったものを拾ってくる場合もあります。
- 卵、幼ダニ、若ダニ、成ダニの各発育期をもち、それぞれのダニはわんこの皮膚を穿孔し、トンネルを作って生活をします。皮膚の中にいるダニの穿孔、分泌物のためにわんこは強いかゆみを感じます。
- 耳のふちや顔、ひじ、ひざ、かかと、足先から発症しやすく、そのうち全身に広がって湿疹様の皮膚炎を起こし、発赤、水疱、小結節、かさぶた形成、皮膚の肥厚、脱毛、落屑や細菌の二次感染などが起こってきます。
- おそろしく痒いのでパピーでは、その痒さのための食欲減退、発育遅延で死亡することもあります。
- 接触によって他の犬に感染するので、症状が改善されるまでは、他の犬との接触を避けてください。また、ママたちにも感染する事があり腕や腹部、大腿などに湿疹ができます。
- ダニを殺す作用のあるシャンプーを使ったり、その子の寝ているベッドなどの消毒、一緒にベッドで寝ている場合はベッドも殺虫剤などで消毒してくださいね。ダニが完全に死滅すれば完治します。
Nail Ticks ツメダニ
- ツメダニはたたみ、じゅうたん、ふとん、ぬいぐるみ、その他の布製品と藁製品に生息します。6月-9月の高温多湿の時期に多く発生し、寒い冬でも死滅することなく、暖房によって繁殖します。お家の中で生息するダニで最も多いものです。(このダニは埃の中のコナダニ、ヒョウヒダニなどを食べて生息します。ヒョウヒダニはアトピー性皮膚炎や喘息の原因になるダニです)新築後2-3年の家屋に多いため、カラオケ屋さんや電車などで拾って来て飼い主さんが媒介する場合も多いのです。
- 非常に痒いものです。皮膚が赤くなってかさぶたのようなぶ厚いフケが重なったような状態になり、そのフケをめくると小さなツメダニがたくさん寄生しています。毛の先端にツメダニが付着している場合は白い粉がふいているように見えます。毛も抜けやすくなります。
- ダニを殺す作用のあるシャンプーを使ったりして分厚いフケを完全に洗い流してください。ダニ駆除も行います。丸刈りにすると完治も早い場合があります。
Ticks マダニ
- 世界中には約800種類のマダニがいます。季節的なものや湿度などによって突然大量発生する事がありわんこだけでなく他の動物にも突然大量寄生することがあります。
- ダニは草むらの葉っぱの先に上ってわんこの身体にジャンプする機会を待つんですよ。それからわんこの身体の吸血しやすい場所を探して移動します。やわらかくて噛みやすい毛の少ない所で、お耳の内側や眼の周り、おしりの周り、内股、手足の先などを噛まれるケースが多いようです。(一番発見度の多いのがお耳の端っこなど顔の周りです)
- 噛まれると強い刺激とかゆみが生じ、多量の吸血が栄養障害や貧血までも引き起こします。マダニが吸血するとその身体の大きさは100倍以上もになることがあります。マダニは、血液中の栄養素をその身体の中で濃縮したあとで、大量の水分を唾液として宿主の身体の中に吐き戻します。これが周囲の細胞の溶解と壊死を起こしながら原虫、細菌、ウイルス、スピロヘータ、リケッチア(動物に寄生して生きるのが特徴の細菌です)など多くの病原体を媒介します。噛まれたところが炎症を起こすと炎症性肉芽腫にまで悪化する場合もあります。
- バベシア症を引き起こすスポロゾイトは、マダニの吸血が刺激となり、36時間から48時間以内に成熟して感染力を持つようになります。血液を介して病気の原因となる原虫が媒介され、この原虫は血中の赤血球を破壊します。ママわんこがこの原虫に感染するとお腹の中のパピーにまで血液を通して感染します。貧血、発熱、食欲不振などを起こし、急性例では死亡する事もあります。
- ライム病の原因であるボレリアスピロヘータは人間にも感染するので問題になった病気です。こちらでは鳩に寄生したマダニが媒介しました。これは72時間以降に発熱、全身性の痙攣、起立不能、歩行異常や神経過敏な関節炎、および遊走性皮膚紅斑、良性リンパ球腫、慢性萎縮性肢端皮膚炎、髄膜炎、心筋炎など重篤な症状が出ます。(これはわんこよりも人間が感染してこちらでは深刻な問題になっています)
- ヘバトゾーン症は、この病原体をもったダニに噛まれることによって感染しますが、ママわんこからの感染の可能性も指摘されています。症状は発熱、衰弱、貧血、下痢、食欲不振、歩行異常や腰痛を伴う筋肉の知覚過敏、目やに、鼻汁などで免疫低下状態のわんこが罹りやすいと言われます。
- 1匹のマダニが産み落とす卵は、一生で2000~3000個にもなり、1ヶ月ほどで成虫に育ちます。メスは血を吸ったあとで産卵を開始しますので、見つけたら絶対に潰さずにカンシなどで丁寧に捕り、熱湯で殺すか、トイレに流してください。吸血前のマダニは2-3ミリなので見つけることは困難ですが、グルーミングショップにいた頃、大豆くらいの大きさに膨らんだマダニをよくカンシで捕って潰さないようにトイレに流した事があります。そして1匹見つけたらその卵、さなぎ、幼虫が身体にいる可能性がきわめて高いことを考え徹底的な駆除を行います。駆除後はとにかく予防!これに尽きます。
- しっかりブラッシングと虫除けを行ってダニを付けない、付いても必ず駆除するという習慣をつけましょう。
Ear Mite ミミヒゼンダニ
- ヒゼンダニはツメダニのように刺すのではなく、皮膚に寄生して身体に害を与えます。一般に「耳ダニ」と言われるのはこのミミヒゼンダニのことです。わんこの外耳道内に寄生し、寄生虫性外耳炎を起こします。耳垢は黒く痒みが激しいのでしきりに耳を掻いたり首を振ったりする時は要チェックです。このダニの生活サイクルは3週間なので、その間しっかり治療しないと根治できません。
Flea ノミ
- ノミの卵・幼虫・さなぎ、特にさなぎは、羽化直前の状態で成長を止め、たたみやじゅうたん、たんすの下などで待ち、わんこの振動や体温、二酸化炭素に反応して羽化して飛び移り寄生します。 本当にとことんイヤな生物です。
- ノミが血を吸う際にノミの唾液がわんこの皮膚に入るり、ノミの唾液に含まれる「パプテン」というたんぱく質に対してアレルギー反応が起こり、皮膚炎になります。
- ノミに刺されやすいやわらかい場所に起こります。足の付け根や後ろ足、お腹などに赤い発疹が出来て腫れていたら要注意。滅茶苦茶痒いのが特徴なので、掻きむしって二次感染を起こしたり、その部分が脱毛したりします。
- とにかくノミを徹底的に退治しましょう。ノミが経口的に身体の中に入ると瓜実条虫への感染にもなりますので、とにかく徹底的な予防に心がけてくださいね。
- ノミは見つけたら絶対に絶対に手で潰さないで下さいね。お腹の中の卵が飛び散り、膨大な数の卵を撒き散らすことになります。見つけたら洗剤を入れたお水の中で殺してからトイレなどに捨てましょう。
- ノミを捕ったノミとリコームはきちんと消毒を!そこにノミの身体に付いていた瓜実条虫の幼虫などがいる可能性もあります。これはママにもうつりますよ。しっかり消毒し、その後よく手を洗ってくださいね。
- ノミ取りコームに黒い小さな粒があったらウェットティッシュで拭いてみてくださいね。水分で赤茶色に変化したらそれは大事な我が子の血を吸ったにっくきノミの糞です。
Mold・Fungus・Bacteriaカビ・真菌・細菌
- これらは空気中にもお部屋にもお散歩道にもいます。健康な身体では普通に防御システムが出来ていて感染することもないのですが、体力の低下、免疫力の低下などがきっかけで感染したり、皮膚の上で増殖したりします。
- 皮膚真菌症は糸状菌というカビが原因で起きる皮膚病です。糸状菌が皮膚につくと、毛根の中に菌糸を伸ばして行き、菌糸が入った毛はもろくなり切れて脱毛します。この皮膚真菌症は痒みは伴いませんが俗に言う「円形脱毛症」の原因として多い病気です。
- 黄色ブドウ球菌、連鎖球菌などの細菌によっても皮膚炎が起こります。これらの細菌は普段から皮膚の表面にいるのですが、体力の低下や栄養バランスの偏りによる免疫力の低下、ホルモンの分泌異常などが起こると皮膚の上で一気に増殖します。特に体力を失う夏に発症しやすいのが特徴です。丸く赤い発疹の中央が黒ずんだ状態が特徴で「膿皮症」の原因です。
- 意外かも知れませんが、洗濯機の洗濯槽の裏側に付くカビもアレルギーの原因になります。定期的にしっかり消毒して下さいね。
Seborrhea 脂漏症
- わんこの身体の中のホルモンバランスが崩れるといろいろな皮膚病の引き金になります。これは皮脂腺の分泌異常による病気で、内分泌系の異常、栄養不足、寄生虫感染なども原因となります。
- 皮脂腺の分泌異常過多と分泌不足の両方があり、多すぎると皮膚やコートのべたつき、そこに細菌などの感染を起こした結果の悪臭、逆に少なすぎると皮膚の乾燥が進みフケ症となります。過多の場合はよくシャンプーすることによって改善しますが、皮膚乾燥の場合は保湿効果のあるコーミング剤やシャンプーの使用とともにビタミンAの補給、バランスのいい栄養補給が必要です。
Endocrine (Hormonal) Skin Problems ホルモン代謝異常
- 甲状腺機能低下や副腎皮質機能亢進などホルモンの代謝異常によっても皮膚病は起こります。痒みを伴わないものが多いのですが、知らない間に左右対称に脱毛が起こることがあります。日ごろの皮膚やコートの観察でいち早く病気に気づいてあげることが大切です。皮膚症状以外でも、例えば甲状腺機能低下では太ってきて、気温の変化にも弱くなります。副腎皮質機能亢進では、水をやたらと飲む、食欲旺盛になるなどの症状が出ます。
わんこの皮膚にはいろいろなものができます。 これも「早期発見!早期処置!」に勝るものはありません。 おでき?虫刺され?わからないものはとにかく 大きくなる前にしっかりチェック!!です。 そして、どこにどういったものができているかしっかり把握して 獣医さんにちゃんと確認してもらいましょうね。
チュ~ちゃんの身体におできができた時もどの部位にというのを忘れないように全身写真に印を付けて獣医さんに一つ一つ確認していただきました。 その時のファイルはお勉強室の 「うちの子ファイルを作ろう!」 に載せています。
種類
特徴と処置・注意点など
Sebaceous Cysts皮脂嚢胞
- 皮脂嚢胞とは、袋に入った皮脂の塊のようなもので、どんな犬種でも年齢でも起こり、良性のものです。 (チュ~ちゃんにも16歳の頃に出来て、老犬性イボみたいなものと言われました)
- 皮脂嚢胞は限界まで貯まると中身がにじみ出ることがあり、その場合は時々二次感染につながる場合があります。 分泌物は、通常カテージチーズのような塊の場合やどろっとした液状のものです。
- 内側にむかって破裂する場合もありますので、見つけても絶対に搾りだそうとしたりしないでください。細菌性感染の蜂巣炎になって抗生物質での治療が必要となる場合もあります。
- もしも皮脂嚢胞をが自然に破れた場合は、1日に数回、患部を消毒してください、そして、患部を舐めるのを防いでください。定期的に消毒されて、舐めないでおけば、大部分のこの種の嚢胞は自然に治癒回復します。
- 皮脂嚢胞が皮膚の下にできた場合は壁で仕切られるので、それはなくなりませんが、痛みや違和感はないので放置しても問題ありません。
- 皮脂嚢胞は通常、自然に破れるかそのまま留まるかですが、生活に支障を来さない大きさである場合は外科的摘出は勧めない獣医さんが多いです。
- 毎日のブラッシングで皮膚の新陳代謝を高め、清潔を保つことは、皮脂を脂腺と毛包から自然に流れ出させ続けるのを助けます。そのことは毛包の中に皮脂を詰まらせることによって起こる嚢胞形成を防ぎます。
- 適度な必須脂肪酸を摂取することは、もう一つの重要なステップです。 必須脂肪酸は繊細で(簡単に熱と処理によって破壊されやすい)、加熱食やドライフードだけを食べている場合には特に注意して追加してあげる必要があります。生食を与えている場合は必須脂肪酸は破壊されてない状態で与えられます。
- オメガ3脂肪酸の補給としてオキアミ油(krill oil)やココナッツオイルも推奨されます。 オメガ3必須脂肪酸は皮脂の生産を正常化するのを助けます。
Abscess 膿瘍
- 膿瘍は、膿を含む嚢または塊のことです。 噛み傷や刺創のような皮膚外傷によって皮下にバクテリア感染を起こした場合、免疫システムは患部に余分の白血球を送り、バクテリアと戦わせます。膿はその白血球の死骸です。免疫システムは感染部位の周りで繊維被膜を作ることによって、膿瘍を壁で仕切り、他への感染を防ぎます。このカプセル状になったものが膿瘍ですが、時間とともに、このカプセルの壁は薄くなって、破裂し膿は外に排泄されます。
- 膿瘍は自然な膿の排泄によってなんの治療もなしで回復する場合もあります。
- 膿瘍がまだ破裂していない場合は、膿を排泄させるために、針で突いたり、切開したりの処置が必要です。その場合、全身麻酔または強い鎮静剤を使用する必要があります。
- 膿瘍が破裂して、膿が排泄される状態であれば流れ出るならば、ポビドンヨードやクロルヘキシジンなどで殺菌消毒します。感染予防のために抗生物質が処方されます。
- 患部を温シップすることで、血流を高めることは白血球の供給を増やすという意味で、治癒促進につながります。
- 膿瘍は痛みや腫れを伴いますので、気になって舐めたり噛んだりすることで二次感染を引き起こしやすいので、舐めないようにエリザベスカラーは必須です。
Hematoma 血腫
- 血液が袋状に貯留し、血性水疱として腫れ上がった状態を血腫といいます。 外傷などが原因で血管が断裂して出血し、体外に流出しないと血腫となります。
- 犬や猫の場合は耳たぶの内側に出来ることが多いです。耳ダニを持っている犬または猫は、非常に頻回に頭を振ったり、激しく掻いたりするために、血管を傷つけてしまうことにより、突然耳血腫になる場合があります。
- 処置としてはドレナージや切開によって溜まった血膿を排泄させます。
- 手術による耳の奇形や更なる耳の問題を防ぐ意味でも徹底した予防が必要です。頭をよく振る、耳をよく掻いている場合は、その原因を知り、早めの対処が必要です。耳ダニやノミ予防も合わせて必要です。
Granuloma 肉芽腫
- 俗に言う「舐め壊し」で、lick granulomaとかacral lick dermatitisとも言われます。
- あんよの下の方や尻尾の付け根のような場所、一つの部分を舐めたいという衝動から生じている皮膚疾患です。
- 舐めて舐めて舐め続けていると、その部分は赤くただれ、出血するばあいさえあります。そして結果的には、その部分の皮膚は厚く、堅くなり、その部分は脱毛します。
- 最も一般的な原因は、精神的で、ストレス、退屈、強迫観念に関係があると言われています。その他のまれな原因としては細菌性その他の菌類の感染症もあげられます。特にお留守番時間の長い大型犬によく起こり、深部まで舐め壊して細菌感染を起こす場合もあります。
- 原因は心因性の場合は、お散歩時間を長くするなど、精神的なケアを行います。
- 必須脂肪酸の摂取や抗ヒスタミン剤、低アレルギー食など、その原因によって対応しますが、「舐めさせないこと」が最も大切ですので、エリザベスカラーを使用します。
Papilloma 乳頭腫
- 乳頭腫は、皮膚や腺、粘膜にできるウィルス性の良性腫瘍の一種で、ピンク色でカリフラワーのように見えますが、痛みなどはありません。Pawの指の間にもできます。
- 出血や感染が起こらない限り問題はないので、自然消滅を待ちます。(出血や感染がある場合は切除する場合もあります)
Lipoma 脂肪腫
- 脂肪腫は、成熟した脂肪細胞から成り立つ良性腫瘍です。 脂肪腫は、太りすぎの犬(特にメス犬、チュ~ちゃんにもできました)に普通にみられます。
- 脂肪腫はゆっくり成長して、直径数インチにまでなる場合もありますが、痛みは伴いません。
- 脂肪腫のように見える脂肪肉腫(Liposarcoma)という悪性腫瘍がまれにあります。
- 生活に支障をきたすほど大きくなっている場合は切除しますが、その前にバイオプシーが必要です。
Histiocytomas 組織球腫
- 組織球腫は1歳から3歳までの若い犬にできる良性腫瘍で、ショートヘアの犬種に見られることが多いものです。
- 身体のどの部分にもできますが、痛みは伴いません。盛り上がったドーム型で、その形からボタン腫瘍とも呼ばれることがあります。ショートヘアの犬の上でより一般的です。
- ほとんどのものは1-2ヵ月以内に自然に消えますが、それ以上経っても消えないものは、診断のために切除されるべきです。
Sebaceous Adenomas 皮脂腺腫
- 9歳から10歳のボストンテリアやプードル、コッカースパニエルなどに見つかる良性腫瘍です。
- 皮脂腺腫は、皮脂腺から生じ、まぶたと手足に好発します。大きさとしては通常直径1インチ未満です。
- 皮脂腺腫は、まれに悪性の皮脂腺癌(Sebaceous Adenocarcinoma)になることがあります。 腫瘍が1インチより大きく、表面が潰瘍化し、速く成長している場合は、悪性腫瘍の疑いがあります。
- 問題を引き起こさない限り、小さな腫瘍は摘出する必要はありませんが、大きな腺腫は摘出されるべきです。
Basal Cell Tumors 基底細胞腫瘍
- 7才以上の犬の頭や首に見つかる良性腫瘍です。 周囲の皮膚とは別にはっきりした境界を持つ堅い塊として現れます。
- 腫瘍は、数ヶ月あるいは数年の間存在する場合があります。
- 基底細胞腫瘍の数パーセントは悪性の基底細胞癌(Basal Cell Carcinoma)になります。
- 基底細胞腫瘍は、外科的に広範囲に渡って削除されなければなりません。
- 14歳の時のチュ~ちゃんの皮膚に出来たものはこれではないか?と質問したのですが違っていて、獣医さんからは「Basal Cell Tumorsは一般的ではない」と言われました。
Fibroma 繊維腫
- フィブローマ(繊維腫)は繊維結合性組織から成る良性の腫瘍で、口腔内、皮膚、鼠径部、四肢または皮膚の下に発症する場合があります。
- しこりや堅い塊のように成長しますが、痛みは伴いません。
- 外科的削除が一般的です。線維肉腫(Fibrosarcoma)との判別のために組織診が必要です。
Fibrosarcoma 線維肉腫
- 線維肉腫は、結合組織内に存在する細胞の一つである線維芽細胞細胞の異常な分割の結果から生まれる腫瘍で、どの年齢でも起こるものです。
- このタイプの腫瘍は軟部組織から発生しますが、 まれなケースとして、線維肉腫腫瘍は骨から発症する場合があり、この場合は骨の構造を弱めることで、骨折や肢の切断にさえ至る場合があります。
- ほとんどの場合、骨の線維肉腫は良性で転移はしません。(一般的な骨腫瘍は良性で、嚢胞と筋肉の問題としばしば誤診されます。)しかし、まれに悪性の場合は、各器官、リンパ節および皮膚に転移するケースがあります。
- 臨床的に、骨の線維肉腫は、骨肉腫(骨ガンのより一般の型)と類似しています。 主な違いは、腫瘍の構造です。 骨肉腫が骨材料から生成されるのに対して、、線維肉腫は繊維様コラーゲン材から成り立ちます。 腫瘍の生検によって骨組織の生産を示すか示さないかで、線維肉腫は確定診断されます。
- 骨に起こるものは長骨、脊柱および下顎に現われるものと頭蓋骨に現れるものの2つのタイプに分かれます。線維肉腫は骨の内部に侵入して、速い速度で分裂するため、非常に危険です。四肢や脊柱に起こった場合は、歩行困難や運動障害、その部位の膨張などが確認され、触診でもわかります。腫瘍が頭蓋骨に発症した場合は、顔が腫れたりひどい痛みが伴います。
- 外傷のない所見のない骨折から診断されるケースもあります。確定診断はX線診断です。また、骨生検はそれが良性であるか悪性であるかの唯一の確定診断方法です。
- 治療は腫瘍の完全摘出で、足を切断しなければならない場合もあります。悪性だった場合は切断しても再発する場合もあります。
種類
特徴と処置・注意点など
Mastocytomas (Mast Cell Tumors) 肥満細胞腫 (マスト細胞腫)
- 肥満細胞腫瘍は犬の皮膚腫瘍の10-20パーセントを占めます。 そしてそのおよそ半分は、悪性です。 ボクサー、ボストンテリア、ブルドッグなどの短頭種の発生率が高いです。
- しかし、肥満細胞腫瘍は、すべての犬に起こりえます。 バーニーズマウンテンドッグには、肥満細胞腫瘍は特に普通にみられ、2種以上の原子価を持つ特徴として遺伝します。
- 肥満細胞腫瘍を発症する犬の平均年齢は、9歳です。 オスもメスもほぼ同じ割合です。発症したうちの10%の子が「複数の」肥満細胞腫を持っています。
- 肥満細胞は、皮膚、血管や筋肉周辺や消化器などに散在している細胞で、体内への異物侵入をキャッチするとヒスタミンやヘパリンなどの生理活性物質を放出して免疫機能を高めて身体を守る働きをしますが、悪性化した際には、これらの生理活性物質が放出されることによってさまざまな合併症が起こります。胃酸の分泌が促進されることによって胃潰瘍や十二指腸潰瘍を引き起こしたり、穿孔を引き起こしたりもします。 実際、肥満細胞腫瘍の犬の80パーセントは、潰瘍を患っているかもしれません。
- 典型的な肥満細胞腫の外見は、赤みがかって、無毛で、潰瘍化したように見える結節性腫瘍です。 腫瘍が穏やかであるか悪性かどうかについて、その外見によって見分けることは不可能です。 小さな腫瘍は数ヶ月あるいは数年の間、何の悪性変化もなく存在する場合があります、そして、突然大きくなって、リンパ節や肝臓や脾臓などに転移する場合があります。 または、最初から速い速度で悪性化してゆきます。 他の現れ方としては完全に皮膚の下に存在して、脂肪腫のように見える場合もあります。 そういった理由で、どんなしこりでも、かかりつけの獣医さんによって早期に必ずチェックしてもらうことが大事です。
- グレードⅠ(高分化型)・グレードⅡ(中程度の分化)・グレードⅢ(未分化型)に分類されます。包皮周囲、会陰部、爪下、肛門周囲、その他の粘膜皮膚部位ではより未分化の腫瘍が発生し予後不良となります。内臓、骨髄では非常に悪くなります。(* 分化=肥満細胞の成熟の度合いで分化(成熟度)が高いほど、予後はよいと言われます)
- グレードとは別に腫瘍の数とリンパ節転移の有無によって、ステージ分けがされています。外科療法は、グレードが低く(高分化型)、他の部位への転移がなく、腫瘍部位の完璧な切除が行われれば完治可能な唯一の治療方法です。十分な組織縁での摘出が困難な、より大きな腫瘍は、手術プラス・プレドニゾンや放射線療法で治療されます。 化学療法や免疫治療を、術後に併用される場合があります。
Squamous Cell Carcinomas 扁平上皮癌
- 扁平上皮癌は紫外線に長時間あたることによって誘発されて、顔や耳、鼻、口唇など身体の色素性領域にできますが、あまり日光にあたらない部分皮膚や口の中にも発生します。
- 慢性の皮膚潰瘍など、慢性的なびらんや、やけどや傷などによる瘢痕のある皮膚に、堅く平らま灰色がかった潰瘍として発生する傾向があります。
- もう一つの現れ方としては、堅く赤い腫れとカリフラワーのような成長としても現れ、その周りは脱毛します。
- 白い肌・ピンク色の肌の子は日焼けに特に注意です。 日焼けによる炎症、皮膚の早期老化、しわ、皮膚癌などはUVB(紫外線B波のことで深層部まで届くもの)が原因です。紫外線に長時間さらされると、皮膚は表皮を厚くして紫外線を遮断するように、自己防衛反応を起こします。この自己防衛反応としてメラニン細胞によるメラニンの産生があります。メラニンは紫外線のエネルギーを吸収して、深い部分の組織にまで届くのを防ぎますが、生まれつき肌がピンクや白の子たちは、このメラニン細胞がたくさんのメラニンを作り出せないので紫外線の影響を身体の深部にまで受けやすく、リスクが大きいのです。皮膚の白い犬や猫は、午前10時~午後2時のUV(紫外線)のピーク時間に外にいることを避けなければいけません。CoCoっちがこの暑いマイアミでサマーカットにはせず、ロン毛にしているのも日焼けから身を守らせるためもあるんです。
- 扁平上皮がんは皮膚にできてから身体の深部に侵入して、進行したステージでリンパ節と肺に転移します。
- 治療としては完全な外科的除去です。 広範囲にわたる病変により完全な摘出ができない場合は、放射線療法をします。
Melanomas メラノーマ (悪性黒色種)
- 悪性黒色腫は、皮膚のメラニン生成細胞から生じます。 メラニン細胞が紫外線によって過度に刺激されると、メラニン色素が過剰に産生されることで、悪性黒色腫の発生リスクが高まります。
- スコッティッシュテリア、ボストンテリア、コッカースパニエルはメラノーマを発症しやすい犬種なので注意が必要です。
- 茶色または黒い小結節は、黒っぽい皮膚エリア、特にまぶたなどで見つかることが多いです。
- 口唇や手足、爪の付け根などでは例外的に無着色の黒色腫が見つかることもあります。
- 皮膚の黒色腫は、通常良性ですが、口に出来るものは非常に悪性度が高いものが多いですです。 爪の付け根に出来る黒色腫のおよそ50パーセントは、悪性で、転移します。 転移は、近くのリンパ節、肺と肝臓に起こります。
- 黒色腫は外科的にその境界までしっかり取り除かれなければなりません。 とても再発しやすいので予後は悪いことが多く、中でも 口にできた黒色腫は最も予後が悪いものです。転移した場合は化学療法を行っても治療の効果はあまり期待できないといわれます。
Perianal Tumors 肛門周囲腫
- 去勢されていない雄犬に発症する肛門周囲の腫瘍は通常は良性の癌ですが、まれに有害な肛門周囲腺癌になることがあり、シベリアンハスキーはこのタイプの好発犬種です。
- 肛門嚢腺腫(Anal sac gland tumors)はまったく別物です。この腫瘍は多くの場合、進行の早い悪性の癌です。それは直腸の両側にある肛門腺から発生し、速い速度で転移します。
- これらの肛門周囲癌は、血液の中でカルシウムの増加に関係しています。
- 治療としては、まず去勢することと、外科的な切除が有効です。外科的切除と放射線治療と化学療法の併用は肛門嚢腺癌に有効です。
皮膚以外のチェックポイントは 「毎日のチェックリスト」 をご参考になさってくださいね。 健康スコアの付け方なども載せていますので、チェックしてみてくださいね。
![]()

暑くなってくると痒い痒いになったり、 免疫力が低下して、ポツンとなにかできたり・・・ でも「できるだけ早く発見」してあげることで悪化予防はできます。 今日もいっぱいハグハグ、 タッチタッチで愛情いっぱい込めながら 全身のチェックをしてあげてくださいね。 CoCoっちに対しては気を付けてあげていても 自分はめっちゃくちゃ紫外線を浴びまくっているママ。 今回いろいろ調べながら「え?もしかしてあの症状はこれ?」と ちょっとドキドキしながらまとめました。 もしかしてこの脇の鈍痛はリンパ節への転移?とか・・・(<ただの筋肉痛です) 心配しすぎもいけませんが、「知っておくことも大事」なので、 ちょっと気になるときに見ていただけたらと思います。
知りすぎると又それも新たな不安の種になったりしますが、「病は気から!!」です。 ママもわんこも元気にハッピーに過ごして ポジティブエネルギーで全身をしっかり守りましょうね~! 今日も元気いっぱいにGo~!
May.2012
![]()
© Paw Paw Club Inc. All rights reserved.