 わんこの糖尿病って?
わんこの糖尿病って?
糖尿病はブドウ糖の代謝異常によって起こる病気で、 炭水化物(糖)やタンパク質などの栄養が細胞に吸収できずに 血中に残ってしまい、最終的に尿中に出てしまいます。
わんこで最も多い内分泌疾患の1つで、年々増加傾向にあります。1999年には1万匹のうち58匹という割合でしたが、 現在では100匹-500匹に1匹は糖尿病の可能性があるとさえ言われています。 にもかかわらず、犬の糖尿病において、国際的評価基準が未だないのも現実です。 わんこの糖尿病は人間と同じように遺伝性のものもありますが、 その他の原因でインシュリンが不足して起こることが多くあります。 インシュリンの絶対的な不足によるものをタイプ Ⅰ 糖尿病と言います。 また、インシュリンは分泌されていても その働きが十分に行えないために発症する場合もあります。 インシュリンは足りているのに働きが十分でない場合をタイプ Ⅱ 糖尿病と言います。
インシュリンが分泌されない TypeⅠDM (Insulin-dependent diabates = IDDM)
要因と症状
- わんこの糖尿病のほとんどがこちらのタイプ Ⅰ 型と言われます。
- インシュリン依存性糖尿病で、膵臓のランゲルハンス島の膵β細胞(インシュリンを作りだす細胞)が自己免疫により破壊されてしまい、インシュリンの生産ができなくなる為に絶対的なインスリン不足に陥る自己免疫疾患です。自己免疫疾患とは、自分の細胞(この場合は膵臓のβ細胞)を自分の身体が異物と判断して攻撃してしまうことで起こる障害のことです)
- お水をがぶ飲みするようになった・おしっこの回数が増えた・おしっこが間に合わないことがある・食欲がすごく増えた・すごく良く食べるのに痩せてきた・だるそうに寝てばかりいる・・・などの糖尿病の症状があります。
診断と治療法
- 空腹時の血糖値を何回か計測して判断します。空腹時血糖が150mg/dlを超えている場合は糖尿病と診断されます。
- 尿に糖が出ているかを調べます。(空腹時または食後2時間以上たった状態の尿で調べます)
- 治療にインシュリンの投与が必要です。インシュリンは通常1日2回接種します。獣医さんで量を決めてもらったら指示に従って毎日お家で皮下注射を行います。(インシュリンは冷蔵庫保存)
- ヒト・インスリンはわんこの糖尿病を治療するのによく使用されますが、ヒト・インスリンが治療に使用される場合は「N」と呼ばれる「Humulin NPH (isophane insulin suspension)」です。犬のインシュリンの構造はヒト・インスリンと微妙に異なっています。その点では、ブタインシュリンが有益であるとも報告されています。
- インシュリンは血糖をコントロールします。少なすぎては効果がありませんし、多すぎれば低血糖症状を起こして危険です。量は獣医さんの指示量を守り、インシュリンの効果が最も高く現れる時間帯に起こりやすい低血糖時の対処方法(蜂蜜を指で口の粘膜に塗るなど)やどの時間に間食をあげるか、どういった状態の場合は必ず受診が必要か(ER)など、インシュリン療法に必要なインフォメーションを全て聞いて理解しておいてください。
- 食事の摂取カロリーなども計算し、(食事のカロリーによってインシュリンの必要量も変わります)、尿チェック、血糖チェックなどのモニタリングをしっかりとして受診の際には報告、獣医さんとの二人三脚で治療します。(必要事項を書き込んで、毎日の記録も付けられるノートを準備しましょう)
- 毎日の適度な運動は必要です。
- 食事は単糖類を多く含むセミモイストタイプのフードを避け、ハイクオリティのものをあげてください。
インシュリンが分泌されても働かない TypeⅡDM (Non-insulin-dependent diabates = NIDDM)
要因と症状
- インシュリン非依存性糖尿病で、治療にインシュリンの投与が必ずしも必要としないタイプの糖尿病です。食事療法や生活の改善で血糖値を正常範囲に維持することが可能です。
- お水をがぶ飲みする・おしっこの量が増える・食欲が異常に増えるという症状が必ずしも現れるわけではありません。
- 女の子の場合、プロゲステロン(黄体ホルモン)が多く分泌されるヒートの後の発症が多いことから、プロゲステロンとの関係も否定できません。ヒートの後に偽妊娠などでホルモンバランスを崩しやすい子は特に注意。ホルモンバランスを崩すことでインシュリンの作用が弱まってしまいます。放っておくと糖尿病に移行してしまう場合があります。
- ホルモンバランスの崩れやすいシニアの子に発症することが多いです。シニアの避妊していない女の子の糖尿病発症率は男の子の4-5倍とも言われます。(男の子も去勢していない子の方が発生率は高いです)
- 副腎皮質機能亢進症など内分泌障害でインシュリンの働きが阻害される場合にも糖尿病になる場合があります。
- ステロイド、プロゲステロンなどのホルモン薬の使用が誘因となる場合もあります。
- クロミウム(クロム)の不足。シニアになるとクロミウムが不足してくるので血糖が高いままでインシュリンが分泌されることでインシュリン血症となりインシュリンの働きが鈍くなってしまいます。
- 歯周病などの炎症や感染症はTNF-αをどんどん産出している状態イコールインシュリン抵抗性を高めているということになります。
- 肥満は最も多い原因の一つです。女の子の場合、妊娠がきっかけになることもあります。肥満になると脂肪組織が増えることでホルモンの働きが鈍くなります。このことはホルモンの分泌を刺激しますが、この状態が続くことで内分泌管に負担がかかり、しだいに分泌不全となってゆきます。若い頃から脂肪分の多い食事を避け、膵臓への負担を減らしましょう。
診断と治療法
- 空腹時の血糖値を何回か計測して判断します。空腹時血糖が150mg/dlを超えている場合は糖尿病と診断されます。喘息やアレルギーなどの病気があってステロイドなどの薬物を使っている場合なども高い値を示すことがありますので、注意が必要です。
- 尿に糖が出ているかを調べます。(空腹時または食後2時間以上たった状態の尿で調べます)
- 理想体重の維持に努め、太らせすぎないように普段から気をつけましょう。
- 食事のカロリーは適切ですか?おデブな子は食事制限も必要です。
- 偽妊娠を繰り返している子は避妊手術をすることで、糖尿病の症状がなくなる場合もあります。
- 規則正しい生活と運動を心がけ、身体のバランスを調えます。
- シニアになってきたら特に栄養バランスに注意し、同時に免疫力を落とさないようにしましょう。
 糖尿病とインシュリン
糖尿病とインシュリンインシュリンの働き
- インシュリンは糖や脂肪の代謝に関与するホルモンです。食事をする→消化されてブドウ糖が血中に吸収される→血糖値の上昇→膵臓のランゲルハンス島からインシュリンが出る→インシュリンとインシュリン受容体が結びつくことによってブドウ糖が細胞内に吸収される→上昇した血糖値が正常値に戻る・・・という働きをします。
- 血液中のブドウ糖の量(=血糖値)を一定に保ちます。
- 肝臓に蓄えられたグリコーゲン(ブドウ糖から肝臓などに貯蔵しやすい物質に合成された形のもの)がブドウ糖(炭水化物から分解されてエネルギー源となる形のもの)に分解されるのを抑制します。
- 肝臓や筋肉でブドウ糖がグリコーゲンに合成されるのを促進します。
- 筋肉や脂肪細胞に血液中のブドウ糖を運びます。
- 脂肪細胞でブドウ糖が脂肪に合成されるのを促進します。(グリコーゲンに変換しきれずに余ったブドウ糖は脂肪として合成されて脂肪細胞に蓄えられます)
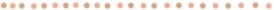
 糖尿病の経過
糖尿病の経過インシュリンが不足すると血中に糖が増える→腎臓で代謝 →尿中に排泄しようと水分も多量に出る→のどが異常に乾く →お水をがぶ飲みする→飲水量が足りないと脱水症状を起こす。
インシュリンが不足するとタンパク質の代謝と吸収がうまくゆかなくなることと尿量が増えることで、尿中に多量のタンパク質が流れ出てしまう →食べても食べても太れない(食欲は増加)→ちゃんと栄養にならないのでとても疲れる →全身倦怠感インシュリンが不足すると脂肪の代謝と吸収がうまくゆかなくなる →脂肪は貯めこまれずに分解される →脂肪が分解する時にできる「ケトン体」という有毒物質が増える →ケトアシドーシスになる。 膵臓から分泌されるべきインシュリンの分泌量が減ると、 (またはその働きが阻害されると) 細胞は血中のブドウ糖を吸収できなくなります。 その結果として血中に糖が増え、血糖値が高くなります。 (正常な犬の血糖値は60-125mg/dl、糖尿病の犬では150mg/dl以上)
血中の糖は最終的に腎臓で代謝・再吸収されますが過度に血中に残りすぎた糖は腎臓で代謝しきれないまま、尿中に排泄されます。 これが「糖尿病」と言われる理由です。 つまり糖尿病とは、簡単にいえば「糖の代謝ができない状態」です。 適切な治療がなされないと非常に危険な糖尿病性ケトアシドーシスとなります。 糖尿病性ケトアシドーシス (DKA=Diabetic ketoacidosis) とは インシュリンの絶対的な不足によって引き起こされる アシドーシス(血液が酸性に傾く状態)のことで 主にⅠ型糖尿病に起こる症状です。 ブドウ糖の代謝が出来ないので細胞はエネルギー源として ブドウ糖の代わりに脂肪酸を利用します。
脂肪酸がエネルギーとして使用される際にできる副産物がケトン体で、このケトン体が血中で増えすぎると血液が酸性に傾き、 口渇・多飲・全身倦怠感・体重減少などの症状を悪化させ、 さらに進行すると血圧低下・頻脈・意識障害などを引き起こし、 放置すると命にかかわります。(輸液やインシュリン投与が必要です)
また、インシュリンは糖の代謝だけではなく脂肪・タンパク質の代謝とこれらの栄養素の肝臓への貯蔵促進にも関わっていますので インシュリンが不足すると、これらの栄養素がちゃんと肝臓に取り込まれず、 血中に残ってしまい、そのまま尿中に出てしまいます。 糖尿病は進行すると、神経症・腎症・網膜症・白内障・ 動脈硬化・心臓疾患・尿路障害など様々な合併症が起こります。  合併症を起こす仕組みは以下を見てね。
合併症を起こす仕組みは以下を見てね。
糖尿病は血液の中の糖濃度が下がらない病気です・・・ということは 血液に糖分があるのでドロッとしている血液なので、流れも悪くなります。 血液の流れが悪くなるということは、細胞の隅々にまで栄養分や酸素が スムースに供給できなくなることを意味します。
細胞に栄養や酸素が十分に行かなくなることはつまり細胞の元気がなくなるということ。そうなると抵抗力や免疫力も低下し、感染などにも弱くなります。
感染を起こすとTNF-α(腫瘍壊死因子の一つ)が多く分泌されるのでさらにインシュリンの働きも鈍ります。 そういった悪循環が全身に広がってゆくのです。
歯周病が心臓や腎臓に影響を及ぼすということは「歯磨きのすすめ」に書きましたが歯周病は血糖値を下げるために働くインシュリンの活性を下げてしまい、 糖尿病の誘因にもなりえると言われています。
そして血糖値が下がらない状態が続くと、血液の中に糖がどんどん増え、血液がさらにドロドロになるので、全身への循環が更に悪化する ・・・という悪循環になってしまいます。 そして、その循環障害から様々な合併症を併発してゆきます。
インシュリン抵抗性とは、インシュリンは充分に分泌されているにもかかわらず
その効きめが悪くなっている為に血糖値が下がらない状態で、筋肉や肝臓でインスリンの作用が低下している状態のことです。
インシュリン抵抗性が生じると、骨格筋や脂肪組織などでブドウ糖の細胞内への取り込みが抑えられます。 インシュリン抵抗性の原因物質として考えられているのが、 TNF-α(腫瘍壊死因子の一つ)です。
腫瘍壊死因子(TNF:Tumor Necrosis Factor)は、腫瘍細胞を壊死させる作用のある物質として発見されたサイトカインです。 (cytokine=細胞から分泌されるタンパク質で、特定の細胞に情報伝達をするもの)
TNF(tumor necrosis factor)-α(炎症性サイトカイン)は感染などの炎症時に白血球の単球・マクロファージから分泌されます。 その過剰な産生は敗血症性ショックなどで組織の壊死を引き起こします。 TNF-αは、炎症が起こると多く産出される物質で、 細菌に感染した細胞に炎症を起こさせてダメージを与える物質ですが、 同時にインシュリンの作用を抑制する働きもあります。 また、脂肪細胞からもTNF-αが多く分泌されるため 遺伝性の肥満動物の脂肪組織では、TNF-α遺伝子産生の増加が見られ、 インシュリン抵抗性を起こし、糖尿病が発症します。 蓄積した脂肪組織から分泌されたTNF-αは 筋・脂肪組織や肝臓での糖の利用を抑制して、インシュリン抵抗性を起こし、 糖や脂質代謝の異常を引き起こすと考えられています。
TNF-α抗体を使用してTNF-αの働きを中和するとインシュリン抵抗性は改善が見られます。 (TNF-αはTNF-α受容体に結合してインシュリンの作用を減弱させる) 適度な運動によってもインシュリン抵抗性は改善できます。
これは運動によって身体の中の脂肪細胞が減ることでTNF-αの分泌が少なくなる事によります。
その結果、筋肉中のインシュリン受容体の数が増え、インシュリン受容体の働きも活性化されるためだと考えられています。
* インシュリン受容体とは筋や脂肪細胞などの細胞膜に存在するインシュリンと結合する部分のことで、 例えばインシュリンという鍵が、インシュリン受容体という鍵穴にはまると、 細胞のドアが開き、そのドアからブドウ糖が細胞内に入っていける ・・・という仕組みのようなものです。 この仕組みを支えている(鍵と鍵穴を結合をさせるために働く)物質を Glucose Tolerance Factor (GTF)と言います。
ここでは直接的にインシュリンに関わるものから、 血液を浄化し二次的な感染を防ぐ働きのもの、合併症予防に役立つものなどを載せています。
|
わんこの糖尿病に有効なハーブ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
わんこの糖尿病に有効な栄養素 |
|
|
|
|
|
安全性についての見解 [Natural Health Bible for Dogs & Cats]より |
|
|
|
|
|
|
|
安全性についての見解 [Natural Health Bible for Dogs & Cats]より |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意点 |
|
|
|
 [Home -Prepared Dog & Cat Diet] と [Natural Health Bible for Dogs & Cats] の記述です。
[Home -Prepared Dog & Cat Diet] と [Natural Health Bible for Dogs & Cats] の記述です。(記述の仕方に若干違いがありますが、内容はまったく同じでした) Diet Composition 古い考え方では、糖尿病患者の食事の炭水化物は制限されるべきと 主張されてきましたが、現代においてはこれは正しいと考えられていません。
*** 糖尿病の犬の食事は以下のバランスを推奨します ***50-55%
炭水化物(但し蔗糖などの単糖類を一切含まず でんぷんと食物繊維で構成されること)
20%
脂肪
15-30%
タンパク質
炭水化物は犬のエネルギー源として最適です。 炭水化物の種類によっては消化と吸収に時間かかかります。 このことは短時間で多量の吸収を防ぐことになり、 血糖の急激な上昇を抑えることができます。 (早い吸収による血糖の急激な上昇は高血糖症を引き起こします)
炭水化物(ライス以外)の多い食事を与えることは、細胞のインシュリン感受性を高めることにより 細胞のブドウ糖吸収を促進、その結果として高血糖症を改善します。 野菜・燕麦・じゃがいもなどの炭水化物は、 複合糖質やでんぷんの中でも(ライスなどよりも)ゆっくりと消化され、 ゆっくりと吸収されるため、急激な血糖の上昇を抑えられるという意味で 糖尿病の犬の食事に最適な炭水化物です。 (単糖類の砂糖は最も早く血糖の上昇をもたらします) 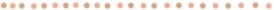
 食物繊維について
食物繊維について食物繊維は別の方向からの改善に役立ちます。 食物繊維は分解されないまま腸に届き、減量に役立ちます。 炭水化物の消化を遅くすることでグルコースの吸収を遅くすることで 血糖の急激な上昇を防げます。 食物繊維には、水溶性のものと水溶性でないもの、 また醗酵性を持つものとそうでないものがあります。 水溶性の食物繊維は水を吸収して胃から食物の動きを遅くする ゲルを形成することによってブドウ糖の吸収をを抑えながら 食物をゆっくりゆっくりと腸に運び、 さらに腸管でのグルコースの吸収を遅らせます。
水溶性でない食物繊維は水を含まない分、やや働きは落ちますが、それでも消化吸収をゆっくりにする働きを持っています。 醗酵性の食物繊維は結腸の腸内細菌に分解されることによって、 短い連鎖を持つ脂肪酸に分解され、栄養分となります。 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のどちらも糖尿病の犬には有益です。 水溶性食物繊維のグアーガム(Guar gum=ゼリーなどの原料となる マメ科植物グァーの種子から摂ったもの)を8g/400Kcalの割合で食事に混ぜることで、 (普通の犬においても糖尿病の犬においても) 食後1時間から4時間の血糖値の上昇を抑えることがわかっています。
不溶性の食物繊維である小麦ふすま(wheat bran)も同じく8g/400Kcalの割合を食事に混ぜることで、水溶性食物繊維と似たような効果があります。 グアーやペクチンなどの水溶性食物繊維を多く与えると下痢を起こす犬もいますが 小麦ふすまは与える量を増やしても便通が良くなるだけで下痢などは引き起こしません。 カボチャや瓜などの野菜類を食事に加えることでも食物繊維プラスの食事となります。 推奨されるのは水溶性と不溶性の療法の食物繊維を混ぜて与えることです。 水溶性の食物繊維はより重要であり、より効果的に働きます。 食物繊維を食事に加えることはインシュリン療法を受けている犬の 血中ブドウ糖を低下させるのにとても有益です。 ただ、「糖尿病で痩せ続けている状態の犬や猫」には 食物繊維は与えるべきではありません。 「体重の維持」が出来てから与えてください。
 糖尿病わんこに推奨される食事の一例
糖尿病わんこに推奨される食事の一例* 1カップはこちらのサイズなので 240ml (8oz) となります
|
食物繊維が豊富で炭水化物たっぷりの低脂肪食 |
|
12-13パウンド(5.3-5.8kg)の子用・452KCal・タンパク質24.5g・脂肪8.9g |
|
|
14-15パウンド(6.3-6.8kg)の子用・512KCal・タンパク質45.8g・脂肪10.2g |
|
 糖尿病にゃんこに推奨される食事の一例
糖尿病にゃんこに推奨される食事の一例* 10パウンド(約4.5キロ)のアダルトにゃんこ(室内飼い)の場合は最大300Kcal、 同じ体重の外飼いのにゃんこの場合は360Kcal、 子猫の場合は300Kcalが1日に必要なカロリー量です。
|
食物繊維が豊富で炭水化物たっぷりの低脂肪食 |
|
471KCal・タンパク質53.1g・脂肪27.4g(チキン挽肉225g&ゆで卵半分の場合) |
|
|
バリエーションとして・・・ |
|
糖尿病の犬にはナチュラルな生食をお勧めします。 食事は1日1回ではなく、 2-3回に分けて与えた方が膵臓への負担を軽減します。
多くの獣医が低脂肪食を勧めるのは、脂肪分解酵素を出す膵臓の負担を軽減する意味からです。 このことは調理された食事において、より重要ではありますが、 過度に脂肪を制限しすぎた食事も良くないので 生肉からいくらかの自然な脂肪を摂るのが良いでしょう。 ブリュワーズイースト(醸造用のイースト)はクロムを多く含むので 糖尿病の犬にしばしば推奨される食材です。 犬のサイズに合わせて小さじ1杯から大さじ1杯を食事に加えてください。 ビタミンEはインシュリンの必要量を減らすことが出来ます。 1日当たり25-200IUの食品ベースのビタミンEを与えてください。 ビタミンCも重要な栄養素です。 体重20パウンド(約9キロ)あたり500gを上限に与えてください。 (最初は様子を見ながら少量から始めて下さい) ニンジンにはナチュラルなインシュリンが含まれています。 生のままジュースやピューレにして与えてください。 リンゴやバナナなどの生のフルーツを食事に加えてあげることは 食事中の食物繊維を増やす意味でも有効です。 牛乳やゴートミルク(ゴートミルク特に良いです)をあげる習慣があるなら 頻繁にあげるようにしてください。
もしもヨーグルトやケーファが作れるならハイクオリティのミルク(オーガニックの全脂肪乳)で作って与えるようにしてください。 スーパーマーケットで売っているヨーグルトは 製造されてから数時間しか効力がないものですので その効力に期待しないでください。 オリーブリーフには血糖を下げる作用があります。 ティにしたものを1日小さじ1杯与えてください。 チャイニーズハーブのfo-ti(Polygonum multiflorum=どくだみ)は 糖尿尿改善ハーブであり、優れた血糖降下剤です。 補正作用があるので長期にわたってあげられる漢方薬です。
その他、ガーリックやバードック(ごぼう)、ダンディリオンなどの血液を浄化するハーブも効果があります。
腺治療は、糖尿病の治療においても使われます。 この治療は、膵臓全体または一部組織を抽出したものから作られたものを使用します。 最近の研究において、「Glandular(腺)サプリメントは生理学的な効果を生むことができる 反応性物質を含んでいる」という概念が支持されてきました。 腺エキスに存在する大きいタンパク質高分子が消化管に吸収されるかどうかといった 懐疑的な質問もあがりましたが、これが可能であるという証拠も証明されています。 したがって、これらの腺高分子は消化管から循環系に吸収されることができ、 標的となる組織に対して生物学的効果を示す可能性が高いと考えられています。 研究によると、それらが身体に注入されると放射性同位元素で識別された細胞が それらの標的となる組織に蓄積することが証明されています。 そしてその蓄積は外傷を与えられた臓器や腺への方が健全な組織よりも急速です。 このことは腺サプリメントが期待される必要条件を満たしていることを表します。 また、特定の破損している器官と腺をターゲットにすることに加えて、 腺サプリメントはペットに特定の栄養分も供給できます。 例えば、腺は他の多くの化学成分に加えてホルモンを含んでいます。 これらの天然ホルモンの低投与量での使用は ホルモン補充を必要としているどんなペットへも効果的ですが、特に軽度の病気 または一つの軽度の器官サポートを必要とする全てのペットに有益です。 腺サプリメントは、また、ペットがホルモンを作り出すきっかけとなったり、 健康の維持に役立ったり、闘病を助けたりする上で働く酵素の源として機能します。 腺サプリメントは、ペットに有益であるとされる活性脂質とステロイドの源であり、 投薬量は、使用される製品によって異なります。
タイプⅠ糖尿病のペットのための従来の治療は インシュリンの注射による血糖降下コントロールです。 大部分のペットには使用されていませんが、 一部では経口的な血糖降下剤を使用する場合もあります。 非インシュリン依存性糖尿病(Ⅱ型糖尿病)のペットにおいては 食物繊維を多く含んだ食事で血中のブドウ糖の値の変動を最小限にとどめ (可能な場合は)適度な運動をしながら、 肥満にならないよう努めることが有効です。
![]()

今回、糖尿病について調べながら、 心臓病を抱えながら糖尿病と診断され、インシュリン療法が開始になった シニアの子のことを思っていました。 シニアになってくるといろいろな病気が出てきて本当に切ないです。 1日も早くコントロールが出来て、合併症を起こさずに長生きしてほしい。 応援しているからね!頑張れ!! こうして調べてゆくと、Ⅱ型の糖尿病は生活習慣病であることがわかります。 わんこの場合はほとんどがⅠ型のインシュリンが必要なタイプだそうですが、 「シニアで肥満」というのは一番病気に弱い体質ということにも気が付きます。
みんなシニアになる前にしっかり運動してマッチョな筋肉犬になっておこうね。
さあ、これからはお日様の元気な夏本番です! みんな食欲を落とさないで、元気に過ごしましょうね! シニアの子は無理しちゃだめですよ。まったりのんびり過ごしましょう。 アレルギーのある子は悪化しやすい時期だけど掻き掻きしちゃだめだよ~! 悪化してしまう前にしっかりケアで乗り切ろうね。
では、みんな楽しく、元気に、ハッピーに夏を満喫しましょうね!
Jul.2009
-
© Paw Paw Club Inc. All rights reserved.



